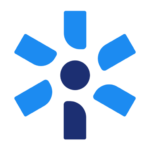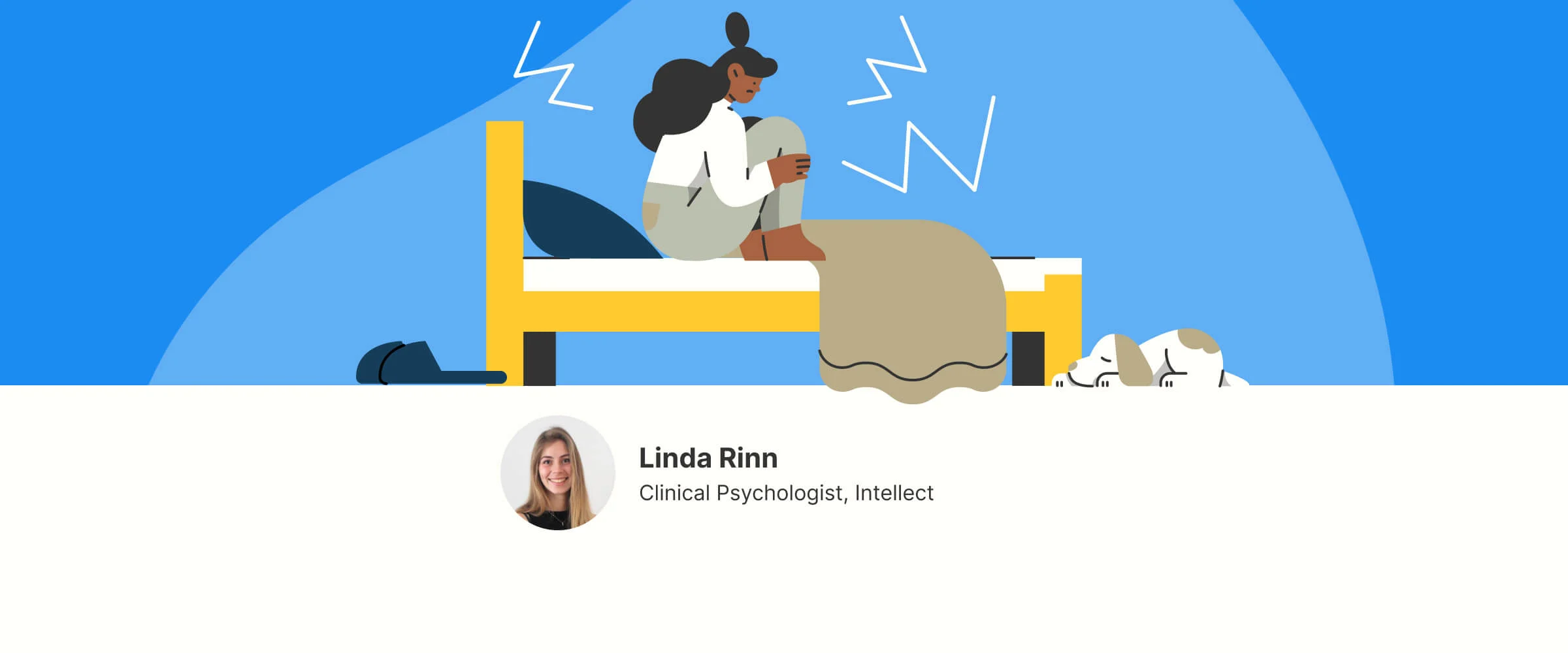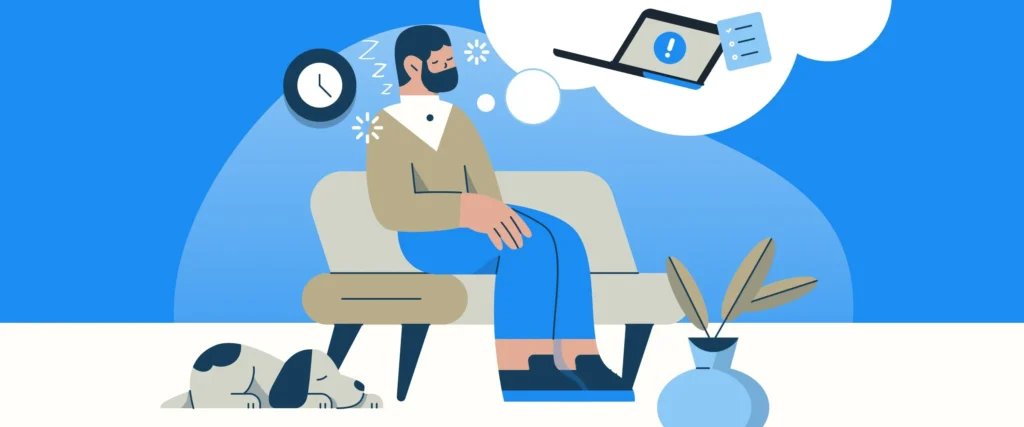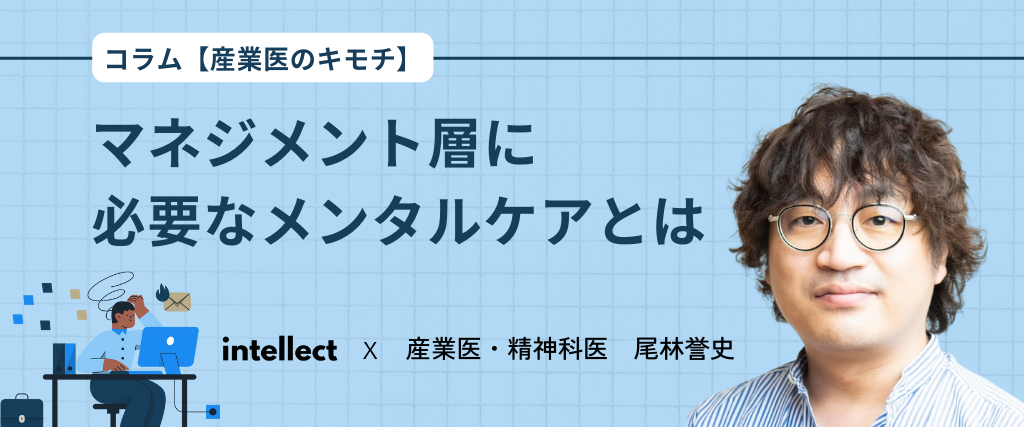質の良い睡眠ほど素晴らしいものはありません。十分な睡眠を取ることでストレスレベルや健康リスクを低減できるだけでなく、集中力や思考の明晰さも向上すると言われています。しかし、特にリモートワークをしている現代人にとっては、質の良い睡眠を毎日とることは難しいものです。
日本人の平均睡眠時間がOECD加盟国の中でワースト1位であり、睡眠不足が経済損失につながっているという報告が出ています。
睡眠不足は、 イライラ、ネガティブ思考、モチベーションの低下など、様々な感情的な影響を引き起こします。しかし、それだけではありません。心臓病、高血圧、肥満などの身体的な健康リスクとも関連があることがわかっています。
もし、夜に眠れず悩んでいるのであれば、この記事で紹介するヒントをぜひ参考にしてください。
良質な睡眠とは?

一般的に、26歳から64歳の成人は 7〜9時間の質の高い睡眠が必要とされています。 国立睡眠財団は、「質の良い睡眠」を以下のように定義しています。
- 寝床に入って30分以内に眠りにつく
- 夜中に1回以上目が覚めない
- ベッドにいる時間の85%以上を眠っている
もちろん、不眠症のような睡眠障害を抱えている場合、これらの条件を満たすのは難しくなります。例えば、不眠症は、週に3回以上、3カ月以上続く睡眠困難の状態を指し、専門家による治療が必要です。ですが、多くの人は良い睡眠習慣を実践することで、睡眠の質を向上させることができます。
「睡眠習慣の改善は小さく単純な変化に思えるかもしれませんが、睡眠習慣について学ぶことは、睡眠障害の認知行動療法(CBT)において不可欠な要素です」と、Intellectの臨床心理士Linda Rinnは説明します。
良い睡眠習慣の効果を実感するには、一貫した実践が必要です。人によって効果は異なるため、自分に合ったものを見つけることが大切です。以下に、Lindaが推奨する6つの方法を紹介します。
良い睡眠習慣を維持する方法6つ
1. 寝室を快適な空間に整える
質の良い睡眠は快適な環境から始まります。散らかっていたり、仕事道具が目に入るような環境は、睡眠の質を低下させます。寝室をきれいに整え、リラックスさせるものだけを揃え、寝室はできる限り睡眠のためだけの空間にしましょう。
入眠に理想的な温度は18〜19度だという研究結果も出ています。温度に加え、光や騒音の影響も重要です。特にルームシェアをしている場合、遮光カーテンやアイマスク、耳栓を使う人もいます。また、BGMとして、ホワイトノイズやその他の音を流す人もいます。
| 色 | 音の種類 | こんな方におすすめ |
| ホワイト | テレビのスノーノイズのような雑音 | 不眠症やADHDの人 |
| ピンク | 雨音や波の穏やかな音 | 睡眠が浅い人 |
| ブラウン | 雷雨や金管のゴロゴロとした低音 | 寝付きが悪い人や騒がしい環境にいる人 |
| ブルー | ねじれたホースのようなはっきりとした音 | 高音に敏感でない人 |
また、就寝時間の少なくとも1時間前には「おやすみモード」をスマホで設定し、画面を切りましょう。スクリーンから発せられるブルーライトによって、体内時計が昼と夜の区別がつかず狂ってしまいます。おやすみモードを使えば、深い睡眠中に不要な通知によって邪魔されることもありません。
2. 睡眠の心理的境界を確立する

「週末の寝だめ」は、実は睡眠リズムを崩す原因になります。週末を含む一週間を通して、睡眠時間と起床時間を一定に保つことが良い睡眠習慣の基本です。たとえ頻繁に夜中に目が覚めても、セットした目覚まし通りに朝は同じ時間に起きましょう。
決まった睡眠のスケジュールを保つことで、「リベンジ夜更かし」を防ぐことができます。日中の時間をうまく使えなかったと感じたり、「自分の時間」が取れなかったという理由から、つい夜更かししてしまう人もいるでしょう。ですが、夜更かしすることで、身体はその日確保できなかった睡眠を翌日補おうとすることになり、悪循環を招きます。
3. 昼寝を戦略的に活用する
Lindaは、精神的にも身体的にも、仮眠は健康とパフォーマンスを大きく向上させると話します。目覚めた状態でくつろぐよりも、短時間の昼寝がより効果的だという研究もあります。
しかし、長すぎたり遅すぎる仮眠はメリットよりデメリットが大きくなります。理想的な仮眠は20分以内で、最適な時間帯は起床の7〜8時間後です。
| 起床時間 | 最適な仮眠時間 | 就寝時間 |
| 5時 | 12-13時 | 20-21時 |
| 7時 | 14-15時 | 22-23時 |
| 9時 | 16-17時 | 23-24時 |
エネルギーが必要な方は、「コーヒーナップ」を試してみてください。カフェインの効果が出るまでに15-20分かかるので、仮眠の直前に一杯のコーヒーを飲むことで、目覚めた時により集中力が高まるでしょう。
4. 適切なタイミングで運動する
睡眠と覚醒は脳の様々な神経伝達物質に影響され、それらの神経伝達物質は食事や身体活動に影響されます。そのため、コーヒーやタバコのような刺激物は就寝時間前は避けましょう。
同様に、適切な運動も正しく行えば睡眠の質を向上させます。定期的に体を動かすだけでなく、午前中に太陽の光を浴びること、そして就寝2時間前の激しい運動は避けることがベストです。仕事の後にしか体を動かせないなら、高負荷の運動ではなく、ヨガやストレッチなどと低〜中程度の負荷の運動にし、就寝時間の2時間前には終わらせるようにしましょう。

5. 就寝前のルーチンを作る
就寝前のリラックス習慣は、質の高い睡眠に不可欠です。就寝前の30〜60分に行い、脳に就寝時間を知らせるための一連の儀式と考えましょう。繰り返し継続することで効果を発揮し、数日続けて実践することで結果がでてきます。
漸進的筋弛緩法:筋肉の緊張と弛緩(脱力)を交互に行い、筋肉の感覚に集中することで、リラックスを意識する方法です。最初は音声ガイドに従い、慣れてきたら自分で行うこともできます。
視覚化:眠りに着く際に、体の様々な部分を頭の中でイメージしていきます。つま先から始め、徐々に体の他の部分へと上がっていきます。
羊を数える:考え過ぎな思考を逸らし、最小限の力で済むことに意識を移行させる、昔からある手法です。
睡眠ジャーナリング:就寝前に、眠りを妨げる考えや懸念を書き出し、頭と心を整理します。また、睡眠を記録することで、自分のパターンや、効果がある就寝前のルーチンを見つけることもできます。
呼吸法:リラックスに欠かせない、実証済みの方法です。例えば、ボックス・ブリージングでは、4秒ごとに息を吸い、息を止め、吐き出し、息を止めます。 また、自分の呼吸のリズムに合わせて、肺で膨らんだり縮んだりする風船をイメージする風船呼吸や、自分が感じたいことや手放したいことを表す色を思い浮かべる色呼吸も試してみてください。
6. 眠れないときは一旦ベッドを離れる
これらの方法をすべて実践しても眠れない夜があるかもしれません。20分経っても眠れないなら、一度ベッドを離れてみましょう。なぜなら、ベッドと寝れないイライラを関連付けないようにするためです。ベッドの上でメールを返信することで、休息の場所としてのベッドの役割を妨げたくないのと同じです。
寝付けないことで失われていく時間を意識するのではなく、ベッドから出て、読書やストレッチなど、暗い明かりの中でくつろげることに取り組みましょう。もちろん、スマホやPCなどのブルーライト画面以外で。

Intellectで睡眠の質を向上させよう
睡眠の問題は人によって異なりますが、適切なアプローチを見つけることが重要です。
もし一人で解決できない場合は、 Intellectアプリのプログラムを活用してみてください。呼吸法、マインドフルネス、ジャーナリングなどのツールをご利用いただけます。さらに、ICF認定コーチや臨床心理士が、眠りを妨げる課題に対してあなたをサポートします。
Intellectと一緒により良い睡眠を目指しませんか?